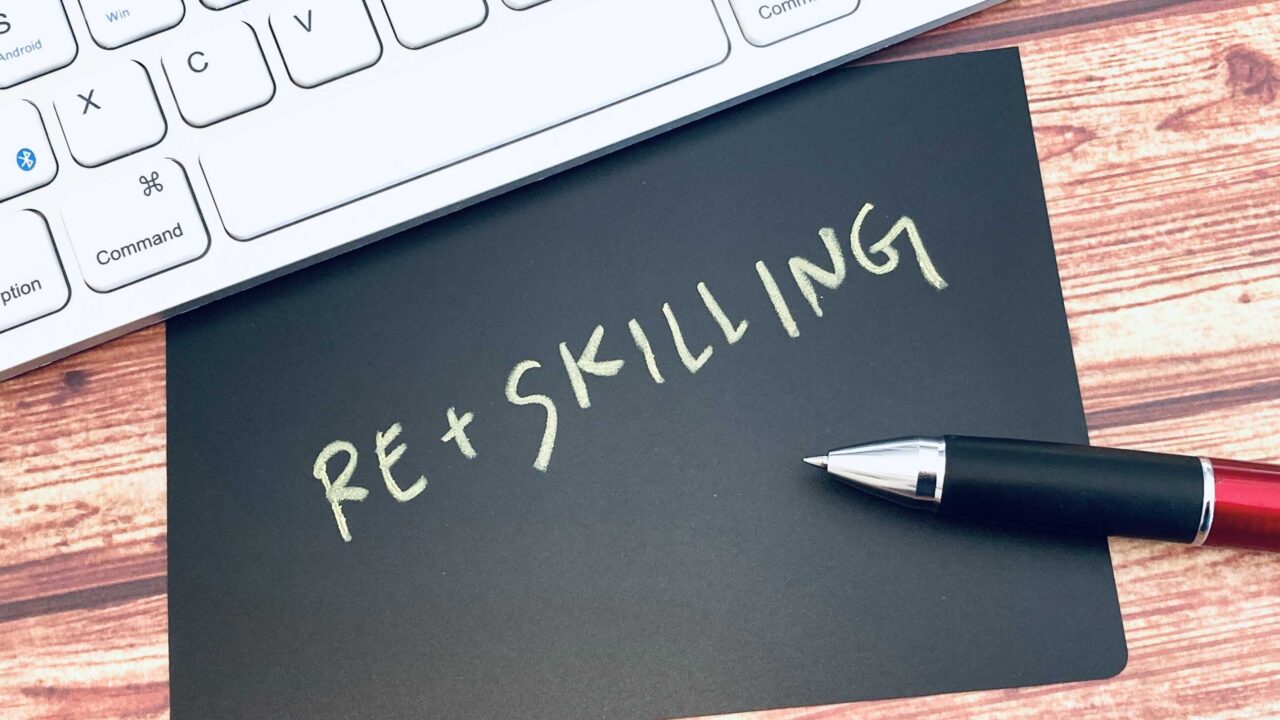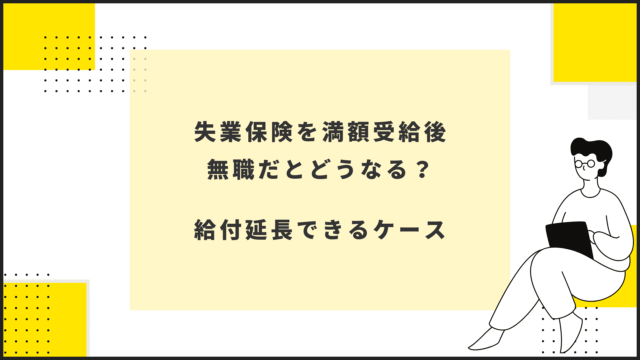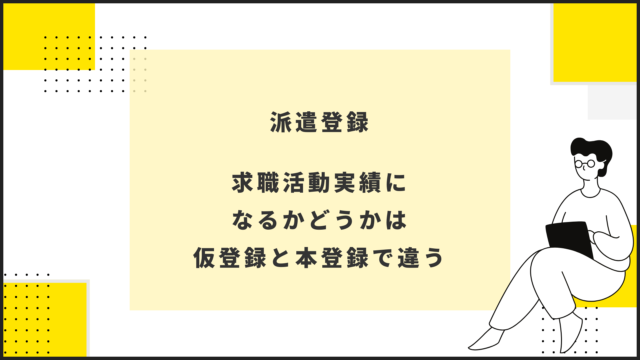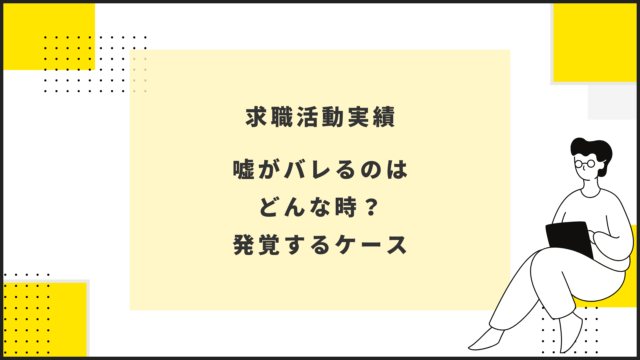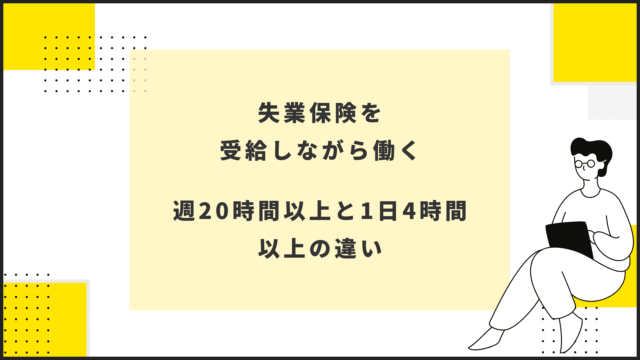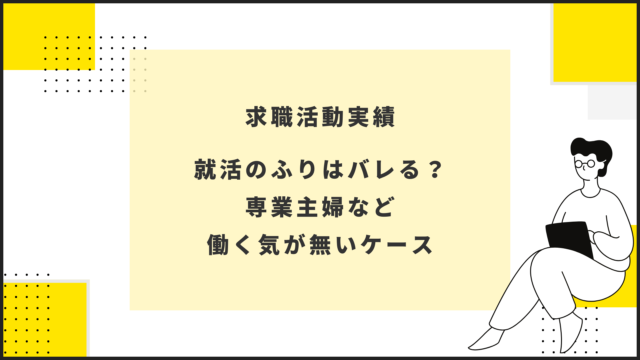リスキリング支援制度を利用して学び直しをしたいけれど、制度が多すぎて何を選べばいいか迷っていませんか?「制度名が似ていて違いがわからない」「自分が対象かどうか判断できない」と感じる人は少なくありません。
この記事では、国が提供する複数のリスキリング支援制度の内容や対象者、厚生労働省と経済産業省による制度の違いについて詳しく解説します。
記事を読むと自分に合ったリスキリング制度を見極められるので、無駄なく制度を活用するための判断基準が手に入ります。リスキリング制度は内容や目的が異なるため、違いを理解して自分に合った制度を賢く選びましょう。
リスキリングとは、今後必要になるスキルを獲得すること
 リスキリングは、英語の「re-skilling」から派生した言葉で、日本語では「学び直し」と訳されます。
リスキリングは、英語の「re-skilling」から派生した言葉で、日本語では「学び直し」と訳されます。
新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること
ー経済産業省「リスキリングとは」
なぜ今リスキリングが注目を集めているのか、国がリスキリングを推進する背景について解説します。
なぜ今リスキリングが注目されているのか?
リスキリングという言葉が一般化したのは、2018年のダボス会議からと言われています。その会議では、テクノロジーの進化によって多くの職業が変化し、既存のスキルだけでは対応しきれなくなることが指摘されました。現代はAIやデジタル技術の発展により業務の自動化が進み、これまで人が担っていた仕事の一部は機械に代替されつつあります。一方で、これに伴い新たな職種や働き方も生まれています。
変化に柔軟に対応し、継続的に働き続けるためには、必要なスキルを学び直す「リスキリング」が欠かせません。そのため、働きながらでも学び直せる環境づくりが注目されるようになったのです。
国がリスキリングを推進する背景
少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口の減少により、人材の確保と育成が喫緊の課題となっています。これまでのように新卒一括採用と終身雇用に頼る人材戦略では、急速に変化する産業構造や労働市場に対応しきれなくなっています。経済のデジタル化・グリーン化が進む中で、新しい分野で活躍できる人材の育成は、産業競争力を維持・向上させるうえで不可欠です。
こうした課題を背景に、政府は「成長分野への労働移動の円滑化」や「労働市場の流動化」を掲げ、リスキリングを重要な政策の柱と位置づけています。現在では、厚生労働省と経済産業省の両省が主体となり、個人や企業を対象としたさまざまな支援制度が整備・拡充されています。
リスキリング支援制度は複数ある!その全体像を整理

リスキリング支援制度は複数あり、名称が似ているものも多いため混乱しがちです。それぞれの違いを正しく理解するには、厚生労働省と経済産業省が提供する制度の特徴を知ることが大切です。
厚生労働省と経済産業省、どちらもリスキリング支援制度を提供している
リスキリング支援制度は、主に厚生労働省と経済産業省の2つの省庁によって提供されています。厚生労働省は、雇用の維持や労働者の再就職支援を目的とし、個人や企業が職業に必要なスキルを身に付けるための支援を行っています。たとえば、「教育訓練給付制度」や「人材開発支援助成金」などが該当し、職業訓練や資格取得にかかる費用の一部を補助しています。
一方で、経済産業省は、成長分野への人材移動や企業の競争力強化を目的に、デジタル分野を中心としたリスキリング支援を推進しています。たとえば「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」では、委託を受けた専門のキャリアコンサルタントや支援事業者が在職者にキャリア相談を行っており、その後、必要な講座を受講する際の費用の一部を国が補助します。
このように、同じ「リスキリング支援」という枠組みでも、それぞれの省庁で目的や対象、支援内容が異なっており、制度を理解するには整理が必要です。
制度の名称が似ていて「わかりにくい」理由
リスキリング支援制度の名称が似ている理由は、目的や内容が重なる部分が多いためです。上述したとおり、リスキリングには「学び直し」という意味があり、一言で「リスキリング」といっても、多くの意味が含まれてしまうからです。
リスキリングと呼ばれる支援制度は、厚生労働省と経済産業省という異なる省庁がそれぞれ独自に制度を設計・運用しています。両者の名称の統一がされていないため、似た印象の制度名が複数存在する状況となっています。
リスキリングという言葉の意味がやや抽象的で幅広いため、制度ごとの名前に明確な違いが出にくくなっています。その結果、制度名だけでは内容の違いが分かりにくく、初めて調べる人にとっては「どれが何を支援する制度なのか」が非常に見えづらいのが現状です。
厚生労働省のリスキリング支援制度とは?

厚生労働省が提供しているリスキリング支援制度には、以下のようなものがあります。
- 教育訓練給付制度
- 人材開発支援助成金
- リ・スキリング等教育訓練支援融資
- 職業訓練受講給付金
「教育訓練給付制度」は、厚生労働省が指定した講座を受講・修了することで、受講費用の一部が支給されます。一般教育訓練、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の3種類があり、それぞれ給付の条件や金額が異なります。
「人材開発支援助成金」は、企業向けの制度です。従業員に対して職業訓練を実施した際に、かかった費用や賃金の一部が助成されます。
「リ・スキリング等教育訓練支援融資」は、求職者や転職希望者が職業訓練やリスキリングを受ける際に必要な受講料や生活費を低利子で借りられる制度です。あくまで融資ですが、条件をクリアすると一部返還免除が認められます。
「職業訓練受講給付金」とは厚生労働省が実施する制度で、雇用保険を受給できない求職者(主に無職の人)が職業訓練を受ける際に、月10万円の生活費と通所手当(交通費)を給付するものです。返済不要で、一定の収入・資産条件を満たし、ハローワークの認定を受ける必要があります。職業訓練受講給付金は、求職者支援訓練などの公的訓練を受ける際に併用される制度です。
どの制度も、失業中の人や働きながらスキルを身につけたい人にとって、学び直しを支える強い味方となります。
4つの支援制度の違いをわかりやすく解説
厚生労働省のリスキリング制度の違いを比較すると、以下のようになります。
| 制度名 | 対象者 | 雇用保険加入 | 支給・融資条件 | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 教育訓練給付制度 | 雇用保険の被保険者または離職後1年以内の者(在職者や離職者を対象に、高度な資格取得のために受講費用の一部を給付) | 必要 | 指定講座の受講・修了で費用の一部を給付 | 事前申請必須/対象講座のみ給付対象 |
| 人材開発支援助成金 | 企業およびその従業員 | 必要(従業員が対象) | 訓練実施で経費・賃金の一部を助成 | 計画届出・報告が必要/中小企業向け枠あり |
| リ・スキリング等教育訓練支援融資 | 求職者・転職希望者(収入等の条件あり) | 不要 | 受講料や生活費の融資(条件により返還免除) | 融資のため返済義務あり/免除要件あり |
| 職業訓練受講給付金 | 雇用保険を受給できない求職者(失業者) | 不要 | 月10万円+通所手当の給付(一定条件あり) | 収入・資産要件あり/ハローワーク認定が必要 |
リ・スキリング等教育訓練支援融資と混同されやすい制度に、求職者支援資金融資があります。求職者支援資金融資は日本政策金融公庫(※所管は財務省)が行っている制度ですが、訓練中の生活費を無利子で貸し付け(返済あり)している融資型の制度です。
ちなみに、リ・スキリング等教育訓練支援融資は、雇用保険(失業手当)が切れた後にも利用できます。雇用保険(失業手当)の受給に必要な「求職活動実績」については、以下の記事で詳しく解説しています。
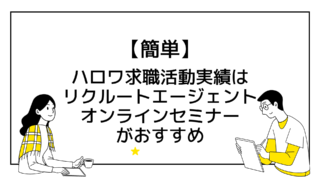
経済産業省のリスキリング支援制度とは?

厚生労働省が提供しているリスキリング支援制度には、以下のようなものがあります。
- リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(通常版|個人版)
- 成長分野等人材育成支援事業(企業向け)
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業について
リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業(通称:キャリアアップ支援事業)は「①通常版」と「②個人版」に分けられます。
| 項目 | ① 受講料補助型(通常版) | ② 給付金型(個人版) |
|---|---|---|
| 支援の形式 | 受講料の一部を補助(割引) | 講座修了後に現金で給付(キャッシュバック) |
| 補助内容 | 受講料の最大70%(上限56万円) | 修了後に最大56万円の給付 |
| お金の流れ | 講座申込時に補助され、自己負担額が減る | 一度全額支払い→後日条件を満たせば給付される |
| 対象者 | 企業などに雇用されている社会人 | 雇用形態に関係なく、一定の条件を満たす個人 |
| 雇用保険の有無 | 必要 (通常、企業に雇用されていることが前提であり、雇用保険加入が要件になるケースが多い) |
不要な場合もあり |
| 対象講座 | 経済産業省が認定した「キャリアアップ講座」 | 同じく経済産業省が認定した講座 |
| 申請タイミング | 講座申し込み時 | 講座修了後(事後申請) |
| 管轄・運営 | 経済産業省・事業実施団体(民間委託) | 同上 |
| 特徴 | 費用の負担を事前に軽減したい人向け | 自己負担できるが後から補填してほしい人向け |
「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」は、経済産業省が実施する学び直し支援制度で、社会人がデジタルや成長分野の講座を受講した場合、受講料の最大70%(上限56万円)まで補助されるのが特徴です。主に現役で働く人が対象で、キャリアアップや転職を見据えたスキル取得を支援しています。
成長分野等人材育成支援事業(企業向け)について
「成長分野等人材育成支援事業」は、経済産業省が実施している企業向けのリスキリング支援制度です。この制度は、企業や業界団体などが、自社の従業員や転職を予定している人に向けて行う人材育成プログラム(研修)に対し、実施費用を国が補助するというものです。補助対象となるのは、講師謝金や教材費、会場費、研修運営に関わる経費などで、成長分野(IT・AI・デジタル・グリーン・脱炭素など)での活躍が期待される人材を育てることが目的です。
たとえば、デジタル分野に強い人材を社内で増やしたい企業が、プログラミングやデータ分析の研修を企画・実施する場合、その費用の一部がこの制度で支援されます。また、事業転換や再編に伴って配置転換が必要なときにも活用でき、従業員のスキル転換を後押しする手段としても注目されています。
この制度は、個人向けの「キャリアアップ支援事業」とは異なり、企業が“人を育てる側”として申請し、支援を受ける点が大きな特徴です。企業が中長期的な視点で人材を育成し、成長分野への人材シフトを加速させるための重要な制度となっています。
厚生労働省と経済産業省の制度の違いについて

厚生労働省の制度は、再就職や生活支援を目的とした学び直しで、離職者や求職者も対象です。一方、経済産業省の制度は、キャリアアップや成長分野への転職を支援する学び直しで、主に在職中の社会人が対象です。目的と対象が大きく異なります。
厚生労働省と経済産業省の、リスキリング制度の違いは以下のとおりです。
| 比較項目 | 厚生労働省の制度 | 経済産業省の制度 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 再就職支援、生活支援 | キャリアアップ、転職・成長分野への移行 |
| 主な対象 | 在職者、離職者、求職者 | 主に在職中の社会人 |
| 支援の内容 | 受講料の給付、訓練中の生活費支援 | 受講料の補助(最大70%) |
| 対象分野 | 資格取得、職業訓練など幅広い | IT、AI、デジタル、グリーンなど成長分野 |
| 管轄 | 厚生労働省(ハローワーク等) | 経済産業省 |
まとめ|制度の違いを理解して賢く活用しよう

リスキリング支援制度は、国が提供する学び直しのための制度ですが、制度の種類が多く、名称も似ているため、どれを選べばよいのか迷ってしまう方も多いです。
厚生労働省の制度は、主に再就職や生活支援を目的としており、離職者や求職者も対象になります。一方、経済産業省の制度は、在職中の社会人がキャリアアップや転職を目指して新たなスキルを身につけることを目的としています。
制度によって対象者や支援内容、申請のタイミングが異なるため、自分の状況に合った制度をしっかりと見極めることが大切です。リスキリング制度の全体像と違いを理解し、今後の学び直しにぜひ役立ててください。