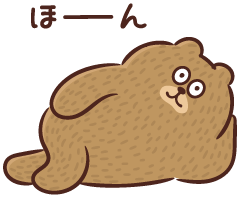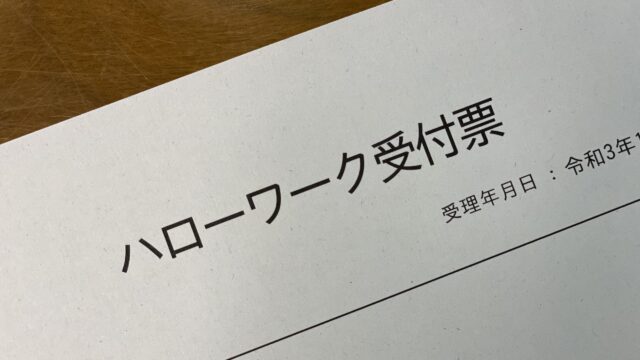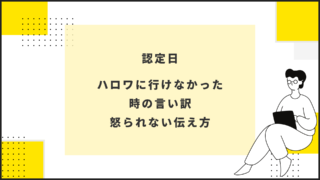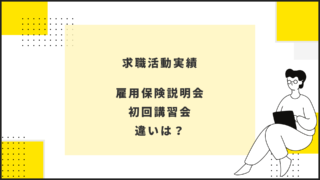ハローワークとは?サービス内容・利用方法をわかりやすく解説
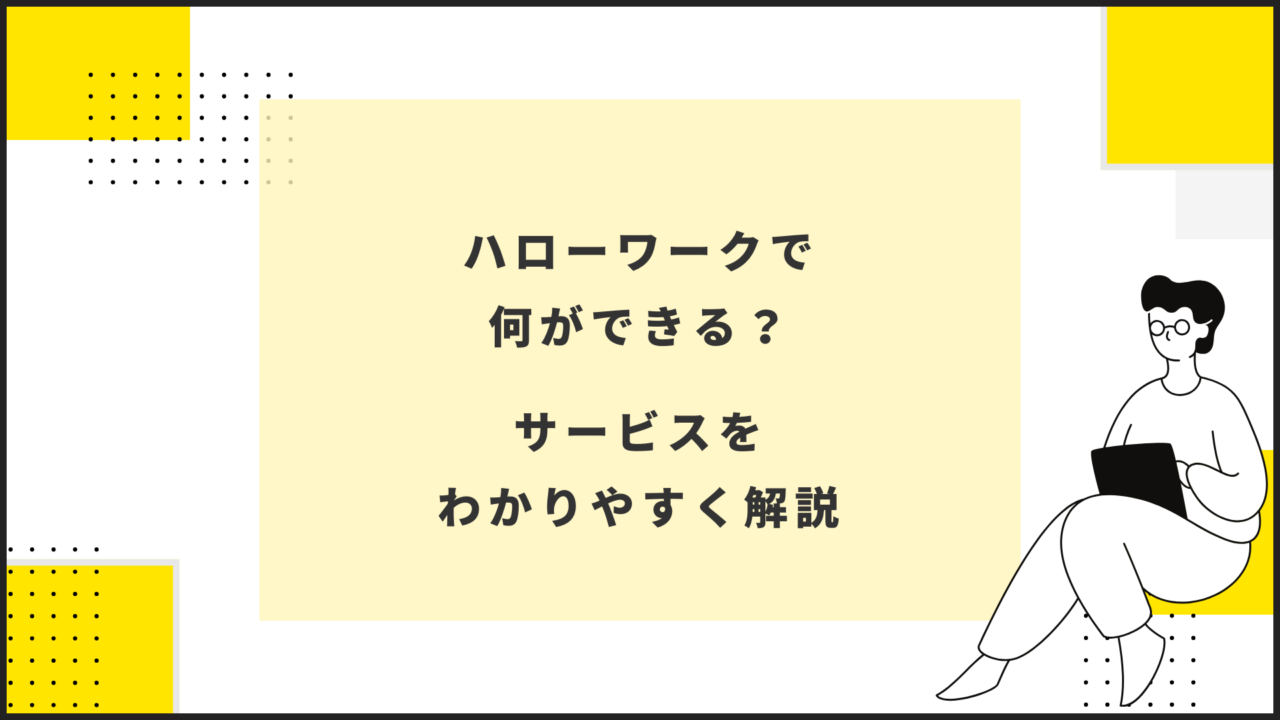
名前:Kei
職業:大学のキャリアセンターで新卒〜既卒・第二新卒の就職支援を担当(現職)
資格:キャリアコンサルタント(国家資格)の他、CDA(キャリアデペロップメントアドバイザー)、進路アドバイザー、メンタルヘルスマネジメントⅡ・Ⅲ種など、キャリアと心理に係る多くの資格を取得。
.jpg) 経歴:大学を卒業後、5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を繰り返した経験から、職業選択の重要性を痛感。現在は大学のキャリアセンターで働き、多くの求職者支援に携わる。
経歴:大学を卒業後、5年間で5回の転職(派遣・アルバイト・正社員含む)を繰り返した経験から、職業選択の重要性を痛感。現在は大学のキャリアセンターで働き、多くの求職者支援に携わる。
ハローワークは、国(厚生労働省)が運営する公的な就職支援機関です。求人紹介や雇用保険の手続きだけでなく、職業訓練や応募書類の添削など、幅広いサービスを提供しています。
ただ、「年配の人が多い場所では?」「求人の質は大丈夫?」といった疑問を持つ方も少なくありません。
この記事を読むと以下のことがわかります。
- ハローワークとはどんな機関か
- 受けられるサービスと利用の流れ
- 対象となる利用者の特徴
- メリット・デメリットや注意点
<求職活動実績や雇用保険の詳細は関連記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください>
ハローワークとは働く人と雇用を支える国の支援機関
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する公的な就職支援機関です。
仕事を探す人と人材を求める企業の双方を対象に、無料で幅広いサービスを提供しています。
ハローワークの主な役割と目的は以下のとおりです。
- 求職者への職業紹介・求人検索の提供
- 職業相談や応募書類の添削サポート
- 雇用保険(失業手当・再就職手当など)の手続き窓口
- 職業訓練や就職セミナーの実施
- 雇用対策や労働市場に関する情報提供
全国のハローワーク数と運営主体
ハローワークは全国に544カ所あり、地域ごとに窓口が設置されています(令和7年4月1日時点)。
»厚生労働省(外部サイト)
一般的なハローワーク(公共職業安定所)の他にも、以下のような利用者の特性に合わせた専門窓口があります。
- 新卒応援ハローワーク(卒業後3年以内の人向け)
- わかものハローワーク(概ね45歳未満の人向け)
- マザーズハローワーク(子育て世代向け)
- 外国人雇用サービスセンター(外国籍の方を対象にした就職支援)
- 福祉人材コーナー(福祉分野の求人や人材確保に特化)
運営主体は厚生労働省で、求人情報は「ハローワークインターネットサービス」を通じて全国共通で閲覧できます。
ハローワークの利用対象者と利用条件
ハローワークは年齢や職業に関係なく、すべての求職者と求人企業が利用できる公的な支援機関です。「失業者だけが行く場所」というイメージがありますが、実際には在職中でもキャリア相談や求人検索を目的に利用できます。
ハローワークの利用に年齢制限はない
基本的な窓口(公共職業安定所)は全年齢対象です。新卒や第二新卒、子育て世代、シニア層まで幅広い層が利用できるように設計されています。
例えば大学を卒業したばかりの学生が「就職活動がうまくいかなかった」と相談に来ることもあれば、40代で転職を考えている人が「地域の求人を探したい」と利用するケースもあります。
同じハローワークでも利用者層は多様です。「若者向け」「子育て世代向け」「外国人向け」など特化した窓口を使えば、さらに自分に合ったサポートを受けられます。
在職中でも利用可能
ハローワークは失業者だけのための場所ではありません。雇用保険に加入していない場合や、在職中の場合も以下のサービスを利用できます。
- 求人の閲覧や検索
- 職業相談やキャリア相談
- 就職セミナーやイベントへの参加
ただし、応募書類の添削や求人への応募といったサービスを利用する場合は「求職登録」が必要です。ハローワークへの求職登録をしていないと、利用が制限されるケースがあるため、本格的に活用したい場合は求職登録をしておくと安心です。
実際、私がサポートしている人の中には「働きながら次の職場を探すためにハローワークを利用した」という人もいました。在職中だからこそ「転職活動をどう始めればいいか」「どんな求人があるか」といった相談に役立つ場面は多くあります。
ハローワークで受けられるサービス

ハローワークでは、以下のとおりさまざまなサービスを受けられます。
- 求人検索・紹介(窓口+インターネットサービス)
- 雇用保険・失業保険の手続き
- 職業訓練・就職セミナー
- 職業相談・応募書類の添削
- 再就職支援(再就職手当など)
求人検索・紹介(窓口+インターネットサービス)
ハローワークでは、全国の求人を検索・紹介してもらうことができます。
窓口では職員の相談を受けながら求人を探せるほか、パソコン検索や自宅のパソコンから「ハローワークインターネットサービス」で求人情報を閲覧できます。
ただし、掲載されるのは「ハローワークが受理した求人のみ」です。そのため中小企業の求人が多く、大手企業の求人は比較的少ない傾向にあります。
また、求職登録をしていない場合は事業所名が非表示になるなど、以下のような制限があります。
| 求人事業所の意向 | ハローワークに 求職登録している |
ハローワークに 求職登録していない |
| 1.すべての利用者に事業所名等を公開する | 〇 事業所名等が表示される |
〇 事業所名等が表示される |
| 2.ハローワークの求職者に限定して、事業所名等を公開する | 〇 事業所名等が表示される |
☓ 事業所名等は表示されない |
| 3.すべての利用者に事業所名等を公開しない | ☓ 事業所名等は表示されない |
☓ 事業所名等は表示されない |
»ハローワークインターネットサービス 事業所名等の公開(外部サイト)
雇用保険・再就職手当の手続き
雇用保険(失業手当)や再就職手当の申請は、ハローワークが窓口になります。
失業手当は、一定の条件を満たした雇用保険加入者が離職したときに、生活の安定を図りながら次の就職活動を進められるよう支給されるものです。
受給には「求職活動実績」を積み上げる必要があり、退職理由(会社都合・自己都合)によって給付制限期間も異なります。
再就職手当は、給付日数を残して就職が決まったときに受け取れる制度で、以下のように残日数に応じて支給率が変わります。
失業手当の給付日数が以下の場合、受け取れる再就職手当の額
- 給付日数の3分の2以上を残して再就職した場合…基本手当残日数の70%
- 給付日数3分の1以上を残して再就職した場合…基本手当残日数の60%
再就職手当は早めに次の仕事が決まった人ほど手厚く支援される仕組みです。
詳しい流れや実績の作り方については、別記事(求職活動実績カテゴリ)で解説しています。
職業訓練・就職セミナー

ハローワークを通じて、国や自治体が実施する職業訓練に申し込むことができます。パソコンや事務、介護、製造など幅広いコースがあり、無料または低額で受講できるのが特徴です。
また、履歴書の書き方講座や面接対策セミナーといった短期イベントも定期的に開催されています。
職業相談・応募書類の添削
求職登録をしていれば、職員に相談できるだけでなく、履歴書や職務経歴書の添削も受けられます。添削は予約制で、1時間ほど時間をかけてアドバイスを受けられるのが一般的です。
再就職支援(再就職手当など)
ハローワークは「雇用のセーフティネット」として、次の職場が早く見つかるよう支援制度を設けています。
その代表例が再就職手当で、給付日数を多く残した状態で早期就職を決めた場合に支給されます。
他にも、求人紹介やキャリア相談を通じて早期再就職をサポートする仕組みが整っています。
ハローワークの利用方法と求職登録の流れ
ハローワークを利用するためには、以下のポイントを知っておく必要があります。
- ハローワークに求職登録する方法と必要書類
- オンライン登録(マイページ)と窓口登録の違い
- ハローワークのサービス利用ステップ
ハローワークに求職登録する方法と必要書類
ハローワークを本格的に利用するには「求職登録」が必要です。登録時には以下のものを持参しましょう。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 雇用保険被保険者証(持っていれば)
- 離職票(失業手当を申請する場合)
求人の閲覧だけであれば求職登録しなくても利用可能ですが、求人を出している会社名が非公開になるなど情報に制限があります。
オンライン登録(マイページ)と窓口登録の違い
求職登録は窓口でもオンラインでも行えます。窓口とオンラインの違いは、以下のとおりです。
- 窓口登録:その場で担当者と面談しながら登録でき、求人紹介や相談につながりやすい
- オンライン登録(マイページ):自宅から登録可能で、求人検索や応募管理がスムーズ。ただし履歴書添削や相談は結局窓口に行く必要があります
ハローワークのサービス利用ステップ
ハローワークを利用するステップは以下のとおりです。
- 求職登録(窓口またはオンライン)
- 求人検索・職業相談(希望条件を整理)
- 応募書類の添削や面接準備(必要に応じて相談)
- 求人への応募・紹介状の発行
- 就職決定後の給付や手続き(失業手当・再就職手当など)
ハローワークのサービス利用のステップを押さえておくと、窓口での手続きやサービス利用がスムーズになります。
ハローワークを利用するメリット・デメリット

ハローワークを利用するうえで、以下のメリットとデメリットを知っておきましょう。
ハローワークを利用するメリット
ハローワークには、他の就職支援サービスにはない強みがあります。
- 無料で利用できる:求職者も企業も費用がかからず、誰でも安心して利用可能
- 地域密着型の求人が多い:地元中小企業や地域限定の求人に出会いやすい
- 公的機関による信頼性:国(厚生労働省)が運営しているため安心感がある
- 多様な利用者を支援:新卒、若年層、子育て世代、障害者など幅広い層に窓口を設置
ハローワークを利用するデメリット
ハローワークはメリットが多い一方で、以下の課題やデメリットもあります。
- 求人の質にばらつきがある:中小零細企業が中心で、福利厚生や給与条件が低めの求人も多い
- 混雑しやすい:窓口は平日昼間のみで待ち時間が長くなることもある
- 時間や労力がかかる:紹介状の発行や手続きに足を運ぶ必要があり、効率性では民間サービスに劣る場合もある
- 企業側のモチベーション差:企業は無料で求人を出せるため、採用に積極的でない求人が含まれることもある
<もっと詳しく知りたい人へ>
ここで紹介したメリット・デメリットはあくまで概要です。
実際の体験談や具体的な求人の傾向については、関連記事で詳しく解説しています。
[ハローワークを利用するメリット・デメリットを徹底解説](内部リンク)
ハローワークを利用する際の注意点

ハローワークは誰でも利用できる便利な就職支援機関ですが、実際に使う際には以下の点に注意してください。
- 求人の傾向を理解する
- ブラック求人のリスクを考える
求人の傾向を理解する
ハローワークの求人は中小企業が中心です。地域密着で働きたい人には向いていますが、大企業志望の学生やキャリアアップを狙う社会人にとっては物足りないケースがあります。
ブラック求人のリスクを考える
「ハローワークにはブラック求人が多い」と言われることもあります。無料で掲載できるため、条件の厳しい求人や採用意欲が低い求人が混ざることがあるからです。学生から「実際に受けた企業が条件と違っていた」という相談を受けたこともあります。
ハローワークの求人は、求人票だけで判断せず、口コミや企業HPを必ず確認するようにしてください。
ハローワークを効率的に使うコツ

ハローワークを活用して就職活動を効率的に進めるには、以下のポイントを意識することが大切です。
-
希望条件を整理してから窓口に相談する
→ ぼんやり相談すると一般的な求人しか紹介されないので、事前に「業界」「勤務地」「働き方」を書き出しておきましょう -
書類添削や相談をしたい場合は予約しておく
→ 飛び込みだと1時間以上待つこともあるため、予約してから行くことをおすすめします -
他サービスと併用する
→ 転職エージェントや求人サイトも並行して使うと、求人の幅が広がり比較しやすいです。
Kei「効率的に使う準備をしてから行く」だけで、結果が大きく変わりますよ。
ハローワークを利用する際によくある質問
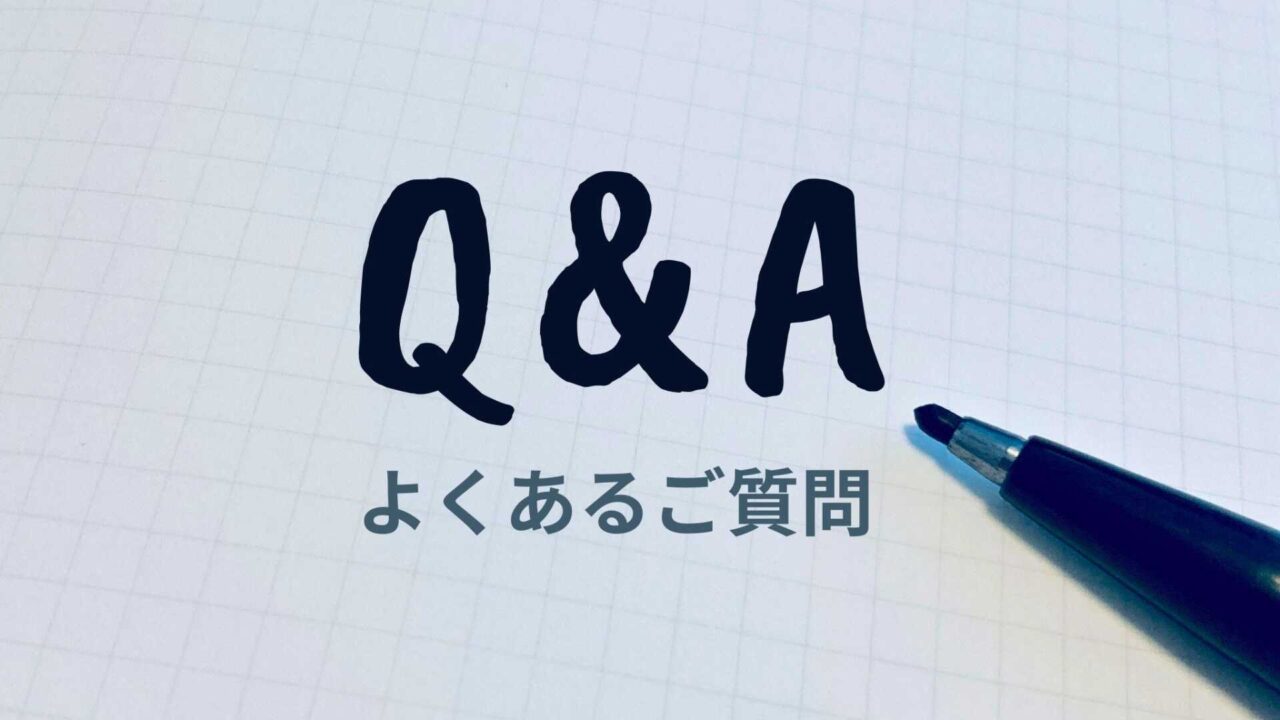
ハローワークを利用するときに多い質問をわかりやすく解説します。
ハローワークの利用に年齢制限はある?
基本的に、窓口(公共職業安定所)は年齢制限がありません。ただし、新卒応援ハローワークやわかものハローワーク、マザーズハローワークなどは対象者が決まった専門窓口のため、年齢制限があります。(詳しくは「全国のハローワーク数と運営主体」を参照)。
ハローワークは在職中でも利用できる?

ハローワークは在職中でも利用できます。求人閲覧や相談・セミナー参加も可能ですが、求職登録をしていない場合は、利用に制限がかかる場合があります(求職登録自体は在職中でも可能)。書類添削は求職登録が必要です。
詳しくは「利用対象者と利用条件」「利用方法と登録の流れ」をご覧ください。
ハローワークの求職登録に必要な持ち物は?
ハローワークの求職登録に必要な持ち物は、本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)、雇用保険被保険者証(あれば)、離職票(失業手当申請時)です。
求人閲覧だけならハローワークへの登録は不要ですが、情報が一部非表示になります。
自分に合うハローワーク窓口はどれ?

ハローワークはさまざまな種類があるので、目的に合わせて選びましょう。どのハローワークを選べばいいかわからない場合は、自宅の近くにある一般的なハローワーク(公共職業安定所)に相談すると適切な窓口を案内してくれます。
ブラック求人を避けるコツは?
ハローワークには「ブラック」と呼ばれる求人も含まれますが、すべてが悪いわけではなく、地元密着の優良企業も多くあります。
求人票だけでは判断できないため、企業HPや口コミ・評判サイトも必ず確認しましょう。
求人票では以下を重点的にチェックすると安心です。
- 条件の妥当性(給与・休日数など)
- 直近の離職率や残業時間
-
給与が仕事内容や地域の相場に見合っているか
迷った場合はハローワークの窓口に相談してください。場合によってはその場で企業に問い合わせてもらえることもあります。
ハローワークのサービスと利用方法のまとめ

ハローワークは、誰でも無料で使える公的な就職支援機関です。求人紹介・雇用保険の手続き・職業訓練・書類添削など、就職活動に必要な支援を一通り受けられます。ハローワークは中小企業の求人が中心になります。求人票だけでは正確に判断できない部分も多いため、企業HPや口コミも併せて確認すると安心です。
ハローワークを効率よく活用するには、求職登録を行い、希望条件を整理してから窓口や専門窓口を利用しましょう。
より詳しい手順や実績づくりは、関連記事(求職活動実績/雇用保険/職業訓練)も参考にしてください。